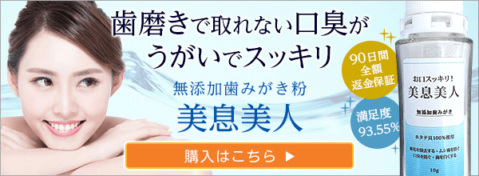こんにちは、口腔ケアアンバサダー(社団法人 日本口腔ケア学会認定)の 上林登です。
「市販のホワイトニング歯磨き粉って、本当に歯が白くなるの?」
コーヒーやワインの着色、黄ばみが気になるけれど、歯医者でのホワイトニングは高額でハードルが高い…そんな時、ドラッグストアで手軽に買えるホワイトニング歯磨き粉が目にとまりますよね。
でも、“毎日使っているのに効果が分からない”“本当に白くなる歯磨き粉はどれ?”“研磨剤や成分のリスクも心配…”そんな声も多く寄せられています。
- 市販のホワイトニング歯磨き粉は、「クリーニングにより歯の表面の着色汚れを落とし、本来の白さに近づける」ことを目的とした製品です。
- ここでいう「クリーニング」とは、
- 毎日のブラッシング(歯磨き)による物理的な清掃
- 歯磨き粉に含まれる成分(研磨剤・ポリリン酸など)による化学的な着色除去や汚れの分解
- 日本の薬機法では「歯そのものを漂白(ブリーチ)して白くする」成分(過酸化水素など)は、市販の歯磨き粉には配合できません。
- メーカーやお店が「ホワイトニング」と表示できるのは、「クリーニング(上記の物理・化学的な作用)による白さの回復」という意味に限られています。
- 歯科医院で行う医療ホワイトニング(漂白)とは、効果も仕組みも異なります。
※「本来以上に白くなる」「漂白」といった表現は薬機法で禁止されています。
市販品の「ホワイトニング」は、毎日のブラッシング+歯磨き粉の成分による“もとの白さへの回復”と理解しましょう。
この記事では、ホワイトニング歯磨き粉の本当の効果と成分の違い、歯科医院との違い、最新研究や専門家の視点から「後悔しない選び方」まで徹底的に解説します。
クリックできる目次
ホワイトニング歯磨き粉の仕組みと限界
1. 市販と歯科医院の決定的な違い
ホワイトニング歯磨き粉は「歯が白くなる」と謳われていますが、その“白くなる”には2つの意味があります。
ひとつは「歯の表面についた着色汚れ(ステイン)を落とすこと」。もうひとつは「歯そのものの色(エナメル質や象牙質の黄ばみ)を漂白して白くすること」です。
実は、市販の歯磨き粉には歯そのものを漂白する効果はありません。
歯科医院のホワイトニングは、過酸化水素などの漂白成分が医療従事者の管理下でのみ使えるため、歯の内側から白くすることが可能です。しかし、ドラッグストア等で販売されている市販の歯磨き粉には、薬機法で漂白効果のある成分(過酸化水素等)は配合できないと定められています。
2. 過酸化水素が入らない理由と薬機法
なぜ市販品には漂白成分が使えないのか?
日本では薬機法(旧薬事法)によって、市販の歯磨き粉には一定濃度以上の過酸化水素や過酸化尿素などの漂白剤が配合できません(※医薬部外品として認可されていない)。
つまり、市販品で「歯が白くなる」とは、主に“表面の着色を落とす”ことを指します。
したがって、元々の歯の色を漂白して明るくすることはできません。これが、歯科医院のホワイトニングと市販ホワイトニング歯磨き粉の最大の違いです。
見た目の白さに加えて、「人と話すときの口臭ケアを市販歯磨き粉で強化したい」という方は、【【市販で選ぶ】口臭に強い歯磨き粉の最強ランキング【2025年版】就寝前に効く低刺激ケア】も参考になります。ホワイトニング系だけでなく、就寝前の口臭対策に強いタイプをまとめています。
主要成分別|ホワイトニング効果と安全性
歯磨き粉成分について詳しくはこちら▶歯磨き粉の選び方:危険を避け、安全性を重視するためのガイド
1. 研磨剤(シリカ・炭酸カルシウム)とRDA値
市販のホワイトニング歯磨き粉の多くは、研磨剤(シリカや炭酸カルシウムなど)が配合されており、歯の表面の着色(コーヒー、紅茶、タバコのステイン)を物理的にこすり落とす仕組みです。
ポイントは研磨剤の「RDA値」(Relative Dentin Abrasivity:象牙質相対研磨性)。これは歯をどれくらい傷つけるかの指標で、「70以下」が一般的に安全とされます。
研磨性が強すぎる製品を使い続けると、歯の表面を傷つけ、逆に着色がつきやすくなったり、知覚過敏の原因になることもあります。
2. ポリリン酸・ピロリン酸のステイン除去
研磨剤以外に、近年注目されているのがポリリン酸ナトリウムやピロリン酸ナトリウム。これらは化学的にステインを浮かせて落とす作用があり、研磨剤による物理的なリスクが少ないのがメリットです。
歯の表面に付着したタンパク質や色素を分解することで、着色をやさしく除去します。
3. ヒドロキシアパタイトが“光を散乱させる”最新研究
もう一つの新しいアプローチがヒドロキシアパタイト(HAP)です。これは歯とほぼ同じ成分で、歯の表面の微細な傷を埋め、光の乱反射を増やすことで「視覚的に白く見える」効果が報告されています。
また、再石灰化を促しながら、歯の表面をなめらかに整えるため、着色やプラークもつきにくくなります。
臨床研究では、「HAP配合歯磨き粉を8週間使用すると、歯の白さ(ΔE値)が明らかに改善した」という結果も出ています。
4. ブルーカバリンの即効トーンアップ原理
最近の注目成分にブルーカバリン(青色顔料)があります。これは歯の表面に微量の青色を残すことで、黄ばみを視覚的に打ち消し、瞬時に歯を白く見せる“光学的ホワイトニング”です。
あくまで一時的な視覚効果ですが、「すぐ白くしたい」「大事な予定前のケア」にも使われています。
ただし、研磨剤のリスクが少ない分、着色除去の根本効果はありませんので、日常ケアとの併用が理想です。
【徹底比較】人気10製品の成分・RDA・臨床データ
ここでは市販で人気の高いホワイトニング歯磨き粉10商品を、成分(研磨剤・HAP・ブルーカバリン)・RDA値・臨床データなど客観的な指標で徹底比較します。
※一部代表例:
- クリアクリーン プレミアム ホワイトニング(RDA:約70/シリカ/ポリリン酸)
- シュミテクト トゥルーホワイト(RDA:約35/HAP/低研磨)
- スマイルコスメティック ホワイトニングペースト(ブルーカバリン配合/RDA:非公開)
- ブリリアントモア(ピロリン酸ナトリウム/中研磨)
- NONIO ホワイトニング(ポリリン酸/中研磨)
- 美息美人(カルシウムなどの成分で再石灰化、アルカリイオン水でタンパク質分解/研磨剤不使用)
低研磨かつHAPやブルーカバリン配合製品は、「削らずに白さをアップ」できるため、特に安全性を重視する方におすすめです。
逆に、「短期間で目立った効果を感じたい」場合は、RDA値が高い(=研磨力が強い)製品を選びがちですが、使いすぎに注意が必要です。
歯科医が教える効果的な使い方と注意点
1. 歯面の再着色を防ぐブラッシング手順
どんな成分の歯磨き粉でも、“使い方”が間違っていると十分な効果が得られません。ホワイトニング効果を高めるポイントは
- 研磨力の高い歯磨き粉は週1~2回まで
- 日常ケアは低研磨・HAPやポリリン酸入りで
- ブラシは強く当てず、軽い力で細かく動かす
- 仕上げにしっかり水でうがいをして、成分を残さない
また、着色のつきやすい「コーヒー・紅茶・赤ワイン・カレー」などを摂取した直後は、特に念入りなケアをおすすめします。
2. 研磨性の高いペーストは週1回に
短期間で白くなりたいからといって、強い研磨剤配合ペーストを毎日使い続けると、エナメル質が薄くなり、むしろ黄ばみや知覚過敏が起きる場合があります。
週1回を目安にポイント使いし、普段は低研磨・成分重視でケアしましょう。
ホワイトニング歯磨き粉で白くならないときの選択肢
1. 歯科医院ホワイトニングとの併用戦略
市販の歯磨き粉で「どうしても歯が白くならない…」と感じたら、歯そのものの黄ばみ(象牙質の着色)が原因かもしれません。
その場合は、歯科医院のホワイトニング(オフィスホワイトニング)を検討しましょう。
歯科医院での施術後に、市販のホワイトニング歯磨き粉で着色を防ぐ「アフターケア」として活用するのが最も理想的です。
2. 美息美人アルカリイオン水との相乗ケア
美息美人は、アルカリイオン水によって、歯の表面に付着したタンパク質汚れ(ステインや舌苔、プラーク)を分解しやすくします。
さらに、カルシウム・リン(ホタテ貝殻パウダー)の働きで再石灰化が期待できるため、エナメル質を強くしながら“歯本来の白さ”を引き出すサポートが可能です。
研磨剤を使わずに口内環境を整え、着色や汚れの再付着も抑えやすくなります。
安全性と効果のバランスを重視する方には、日常のうがいや優しいブラッシングと併用することで、負担をかけずに健やかな白い歯を目指せます。
よくある質問(FAQ)
- Q. 毎日使っても大丈夫ですか?
- A. 低研磨の製品(RDA値70以下)や研磨剤不使用の製品なら毎日使用可能ですが、研磨剤が多いものは週1回程度にしましょう。
- Q. ホワイトニング歯磨き粉で知覚過敏になりませんか?
- A. 研磨剤の強い製品を使いすぎると、エナメル質が傷つき知覚過敏の原因になります。知覚過敏が出た場合はすぐ使用を中止しましょう。
- Q. 歯科医院のホワイトニングとの併用は?
- A. 施術後の着色防止や、白さをキープしたい方に最適です。歯科医と相談しながら選びましょう。
著者から一言アドバイス
市販のホワイトニング歯磨き粉は「歯そのものを白くする」ものではありませんが、正しい選び方と使い方で、表面のステイン除去や口内環境改善には大きな効果を発揮します。迷ったときは、成分や安全性、研磨力をよく確認し、自分に合った製品を選びましょう。もし不安や疑問があれば、いつでもご相談くださいね。
参考文献
- 厚生労働省-歯科用漂白材等審査ガイドラインについて(◆令和05年04月21日)
- ホワイトニング歯磨き粉に配合されている研磨剤とは?-足立優歯科
- 研磨剤入り歯磨き粉は本当に必要?メリットとデメリットを理解し …ノブデンタルクリニック
- RDA 値ガイドライン 厚生労働省-日本人の食事摂取基準(2020 年版)
- ホワイトニング用歯磨剤による着色除去効果の検討-IRUCAA@TDC