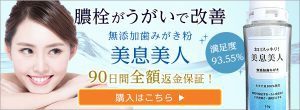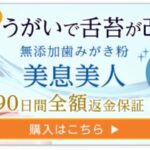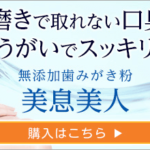膿栓の石化(扁桃結石)
膿栓(臭い玉)とは、扁桃栓子のことですが、石灰化し硬くなったものは 扁桃結石(へんとうけっせき)と呼ばれます。膿栓(臭い玉)の大きさは1ミリ~5ミリ程度で、色は乳白色や黄色です。潰すとドブや硫黄のように臭いので口臭の原因になると思われていますが、そのままの状態では口臭にはなりません。
参考:扁桃結石(膿栓)の画像
膿栓(臭い玉)は、食べ物カスの成分(カルシウムやミネラルなど)が硬くなり、扁桃に蓄積されたものです。
石灰化(石化)は、体液中のカルシウムイオンが炭酸カルシウムなどの形で細胞間に沈着することで起きるため、石灰化するのは膿栓だけではありません。
石灰化には、膿栓のような明らかに良性のものが存在しますが、乳がんのような病的石灰化もあります。
※明らかな良性石灰化には,①皮膚の石灰化,②血管の石灰化,③線維腺腫の石灰化,④乳管拡張症に伴う石灰化,⑤円形石灰化,⑥中心透亮性石灰化,⑦石灰乳石灰化,⑧縫合部石灰化・異栄養性石灰化がある。
引用:医療科学者 マンモグラフィ技術編
今回は、膿栓の石化(石灰化)について詳しく説明しますので、ご参考になれば幸いです。
この記事は、口腔ケアアンバサダー(社団法人口腔ケア学会認定)の上林登が書きました。
クリックできる目次
膿栓が石化(扁桃結石)するメカニズムとは?
口の中から石が出てくる病気とは?
唾石症は、唾液を分泌する唾液腺やその導管内に、硬い石のような塊が形成される病気です。唾液は唾液腺で生成され、導管を通って口内に放出されます。唾液には、口腔内を潤し清潔を保つほか、食べ物の消化を助ける役割があります。さらに、唾液にはカルシウムが豊富に含まれており、このカルシウムが細菌や異物に結合して固まり、唾石と呼ばれる塊を形成します。
臭い玉の特徴
膿栓(臭い玉)は、白や黄色をした小さな塊で、大きさは1〜5mm程度です。質感はチーズのようで、潰すと非常に強い悪臭が漂うことから、「臭い玉」とも呼ばれます。この悪臭は、膿栓が口臭の原因となる一因です。
【症例別】石化の痛み・黒い塊・茶色い塊の正体
膿栓が黒くなる理由とは?
膿栓(臭い玉)は、ふつう乳白色から黄白色をした柔らかい塊ですが、長期間扁桃にとどまると茶褐色や黒っぽい色に変色することがあります。これには以下のような要因が考えられます。
- 血液の混入
扁桃に微小な傷ができたり炎症が起きたりすると、血液がにじみ出ます。その血液が膿栓に付着し、酸化することで色が黒っぽく変わります。 - 石灰化の進行
膿栓が固くなり石化(扁桃結石)する過程で、カルシウムやミネラルなどが蓄積し、色合いが濃くなる場合もあります。 - 細菌・老廃物の蓄積
細菌の死骸や食べかすなどが長期間溜まると、さらに悪臭が強くなり、黒ずんだり茶色に変色することがあります。
痛みがある場合の危険性
基本的には膿栓(臭い玉)自体は柔らかいため、軽い異物感程度で痛みを伴わないケースが多いです。しかし、以下のような症状がある場合は注意が必要です。
- 扁桃炎や扁桃周囲膿瘍の兆候
喉の痛み、飲み込みづらさ、高熱などが続く場合は、扁桃炎が悪化して膿が広がっている可能性があります。扁桃周囲膿瘍は放置すると呼吸困難など深刻なリスクを伴います。 - 扁桃結石の成長
膿栓が石化(石灰化)して大きくなると扁桃を圧迫し、痛みや違和感を引き起こすことがあります。悪化すると手術(扁桃摘出)を要することも考えられます。
少しでも痛みや腫れを感じる場合は、早めに耳鼻咽喉科を受診して原因を特定しましょう。
石化(扁桃結石)の症状
京都府立医科大学病院耳鼻咽喉科学教室が第64回 耳鼻咽喉科臨床学会(大阪)で口演した内容によると、扁桃結石が出来るのはまれであり、これまでのケースで見つかったのは口蓋扁桃だけで、舌扁桃の結石は一例だけだったそうです。
症状としては、咽頭に異物感(違和感)があるが異常はなく、扁桃結石が形成された原因は不明とのこと。また、膿栓や扁桃結石は同じ側の扁桃に再発する症例が多いようです。
膿栓ができたら(膿栓の取り方)
扁桃があるかぎり膿栓は誰にでもできるものですので、喉に違和感があったとしても異常がなければ病気を心配する必要はありません。
たとえ膿栓ができたとしても、ふつうは自然と取れてしまうので、それまで待つことをお勧めします。しかし、口臭が気になるなど早く膿栓を取りたい場合には、耳鼻咽喉科の治療(吸引や洗浄)で除去することもできます。ただし、根本的に膿栓を出来なくするには、扁桃を除去したりレーザーで焼いて穴を塞ぐ手術が必要となります。
膿栓(臭い玉)と口臭の関係!石化を放置してはいけない理由
健康害がなければ、一般的な膿栓はそのままにしておいても問題ありませんが、ケースによっては長期間扁桃に留まることで石化(石灰化)し硬くなることがあります。
Yahoo!知恵袋の質問の中には、喉から茶色の塊りや「黒い石のような塊り」が出てきたという方もいました。膿栓(扁桃結石)の色が濃い場合は、膿が扁桃に長く留まっていたかもしれませんが、血が膿に混じった可能性もあるので、ご注意ください。
唾石症のケースとの類似性
膿栓(扁桃結石)と唾石症の症状は、どちらも石のような塊が形成される点で共通していますが、唾石症は唾液腺や導管に石ができるのに対し、膿栓は扁桃にできる点が異なります。膿栓の石化が進行すると、唾石症のように硬くなることがあります。特に膿栓が黒くなる場合は、扁桃に長く滞在し、血やその他の成分が影響して色が変わった可能性があります。
扁桃腺が腫れたまま放っておくと、「扁桃周囲膿瘍(へんとうしゅういのうよう)」という怖い病気になるかもしれません。これは扁桃腺の中のばい菌が増えて扁桃腺の周囲まで広がり、膿がたまる病気です。
扁桃周囲膿瘍
引用:順天堂大学医学部附属病院
この病気の怖いところは、膿が扁桃腺から喉に広がって気管にまで垂れ、呼吸がしにくくなることです。そのため窒息を引き起こすおそれもあります。
それだけではありません。「膿栓ぐらい」と放置していると、石化して扁桃結石ができることがあります。扁桃炎を何度も繰り返していると、扁桃の中で膿が固まり結石になることもあるのです。
ケースとしてはまれですが、扁桃結石ができると痛みが出る場合もあります。治療も難しく、扁桃摘出手術になる可能性も否定できません。
ですので、膿栓がひどい場合やいつまでも喉に違和感や口臭がある時は、耳鼻科で診てもらうことが大事です。
後鼻漏だからといって放っておくのも危険です。後鼻漏は喉に鼻汁がたれる症状で、軽く考えている人が多いですが、主な原因は副鼻腔炎や鼻炎です。それらを放置すると慢性化するため、早めの治療が望ましいでしょう。
さらに、後鼻漏があると喉に細菌が増え炎症を起こすケースもあります。膿栓や後鼻漏が気になる時には、まず耳鼻咽喉科で受診してください。
石灰化が進行した場合の治療法(扁桃摘出手術)
扁桃摘出手術はどんな人が受けるべきか?
- 扁桃炎を繰り返す方
年に数回、扁桃炎を発症して高熱や激しい喉の痛みを伴う場合、慢性的な炎症を断ち切るために扁桃摘出を検討するケースがあります。 - 扁桃結石が大きくなり、日常生活に支障をきたす場合
繰り返し膿栓ができて喉の違和感が強い、口臭が改善しないなどの場合、レーザー治療や扁桃摘出手術が行われることがあります。
手術の費用・入院期間・術後の痛み
- 費用
保険適用の場合、自己負担率(3割負担など)にもよりますが、数万円~10万円前後が目安です。入院や手術内容によって変動があります。 - 入院期間
通常は数日から1週間程度の入院が必要とされることが多いですが、病院や手術法により異なります。 - 術後の痛み
術後1週間ほどは喉に強い痛みを感じることがあります。飲み込みづらさや発熱が続くこともあるため、医師の指示に従って安静を保ちましょう。痛み止めの服用や、柔らかい食事を中心とした食事制限が必要になる場合があります。
手術を検討する際は、医師と十分に相談し、リスクとメリットをよく理解したうえで決断することが大切です。
膿栓が頻発する人におすすめの日常習慣
- こまめな水分補給
喉を常に潤しておくことで、膿栓の原因となる食べカスや細菌が付着しにくくなります。 - 唾液の分泌促進
食事中によく噛むこと、ガムを噛むこと、お口の体操(舌回しなど)を行うことで唾液の分泌が活発になります。唾液には殺菌・洗浄作用があるため、膿栓の予防につながります。 - 定期的なうがい・ブラッシング
食後や就寝前のうがい、正しい歯磨きや舌苔ケアを取り入れると、扁桃付近にゴミや細菌が溜まりにくくなります。
後鼻漏がある場合の対策
後鼻漏は鼻や副鼻腔からの粘液が喉の奥に流れ込む状態を指します。後鼻漏が続くと、喉に細菌やウイルスが溜まりやすくなり、膿栓の原因となり得ます。
- 鼻炎・副鼻腔炎の治療を優先
まずは耳鼻咽喉科を受診し、後鼻漏の根本原因となる鼻炎や副鼻腔炎を治療しましょう。 - 鼻うがい(鼻洗浄)の実施
生理食塩水を使った鼻洗浄は、鼻腔内や副鼻腔に溜まった汚れを取り除くのに効果的です。 - 生活習慣の見直し
室内の乾燥を防ぐ、喫煙を控える、十分な睡眠をとるなど、免疫力を維持する生活習慣が重要です。
膿の石灰化(扁桃結石)の予防
膿栓や唾石症の予防には、口腔内の健康を保つことが欠かせません。食事の時にはよく噛んで唾液を多く出すようにしたり、お口の体操で唾液腺を刺激することが効果的です。また、酸性化した体質を改善するためには、酢、野菜、海藻などのアルカリ性食品を摂ると良いでしょう。
食事の時にしっかり噛んで唾液を多く出すことや、お口の体操で舌を動かすことは、膿栓予防にもつながります。
膿栓(石化)の予防法はこちらの記事「のどが臭い・対策と予防」が参考になります。
膿栓の石化Q&A
Q1. 膿栓(臭い玉)は毎日できるもの?
A. 個人差があり、扁桃のくぼみが深いと膿栓がたまりやすいです。口臭や違和感が強い場合は受診を。
Q2. 膿栓が石化すると必ず手術が必要?
A. 必ずしも手術になるわけではありませんが、痛み・出血など症状が強い場合は摘出を検討します。
Q3. 扁桃結石ができる前に予防する方法は?
A. 唾液の分泌を促す(よく噛む・水分補給)や口腔ケアの徹底が重要。後鼻漏や慢性鼻炎があれば耳鼻科での治療を受けましょう。
まとめ
痛みや黒い塊が出てきたとき、手術が必要かどうか、どのように予防するかなど、膿栓や扁桃結石にまつわる疑問は尽きません。
- 痛みがひどい場合は早めに受診し、扁桃周囲膿瘍など重大な病気の有無を確認しましょう。
- 手術の要否は症状の程度や生活への支障度合いによります。
- 膿栓や後鼻漏は生活習慣の改善と適切な口腔ケアで抑えられるケースが少なくありません。
膿栓が頻発してお悩みの場合は、一度耳鼻咽喉科に相談し、日常的なケアだけでなく根本的な体質改善を目指すことが大切です。
膿栓と口臭を予防するために、口臭予防歯磨き粉「美息美人」のアルカリイオン水でケアをしましょう。
関連記事:扁桃結石(膿栓)の取り方とコツ!自己流で取るのは危険